

子どもがくじけてしまったら、安心や自信につながるような声掛けをしましょう。 日頃の心がけや声掛けで、くじけない心の基盤になる自己肯定感を育てることができます。
具体的な関わり方と環境の作り方も紹介しますので参考にしてくださいね。
子どもは失敗を通して成長します。 まずは、失敗して落ち込んでいる子どもの気持ちを最後まで聞きましょう。
親御さんに気持ちを受け止めてもらうことで、子どもは「失敗しても大丈夫」と安心します。 また「丁寧に作っているの見ていたよ」「ずっと集中して色を塗れていたね」と、失敗の部分ではなくできていたところを認めてあげると自信に繋がります。
その後で「次はどうしたら良いと思う?」と具体的な対処法を一緒に考えてあげたり「あなたならできると思うから一緒に練習しよう」など励ましたりしましょう。

「すごいね!」と結果だけを褒めるのではなく「頑張って考えたね」「工夫したね」と努力の過程を認めましょう。
成功だけを評価されると、失敗を恐れる気持ちが強くなることがあります。
また、結果に左右されずにいつも同じ態度で関わることも大切です。 結果に振り回されずに接することで「いつでもママ・パパはあなたが大好きだよ」というメッセージを子どもに伝えることができます。
自分が認められていると感じて過ごせることで、自信に繋がるでしょう。
子どもは親の姿をよく見ています。
「苦手だけどやってみるね」「うまくいかなくても大丈夫!」と、親自身が自分を認めながら挑戦する姿を見せましょう。 「失敗しちゃった!」「次は間違えないぞ!」なんて親御さんの人間らしさを堂々と見せると、子どもも「もう一回やってみよう!」と思えるきっかけとなります。
しなやかな心は、家庭の習慣から少しずつ育てることができます。
家庭でのちょっとした習慣でも、毎日続けることで、失敗しながらもチャレンジし続けられるしなやかな心を備えることができるでしょう。

自分の食事を食べきることは、毎日のちょっとしたことかもしれません。 しかし、最後まで食べきるということは、やり遂げる集中力と忍耐力に少なからず繋がっていきます。
ご飯を一粒ずつ残さず食べてからごちそうさまをするなど、最後まで丁寧に食べられるように毎日声を掛けていきましょう。
早寝早起きは、子どもの健やかな生活リズムをつくる基本です。
特に就寝時間が毎日バラバラにならないように、家族で「何時までに寝ようね」とルールを決めて、できるだけ守れるよう声をかけていきましょう。
「ゲームをもう少ししたい」「明日はゆっくりだから夜更かししてもいい?」といった声が出ることもあるかもしれませんが、なるべく生活リズムを崩さないようにサポートしてあげてください。
毎日同じリズムで眠ることが、がんばり続ける心や時間を守る習慣づくりにもつながります。
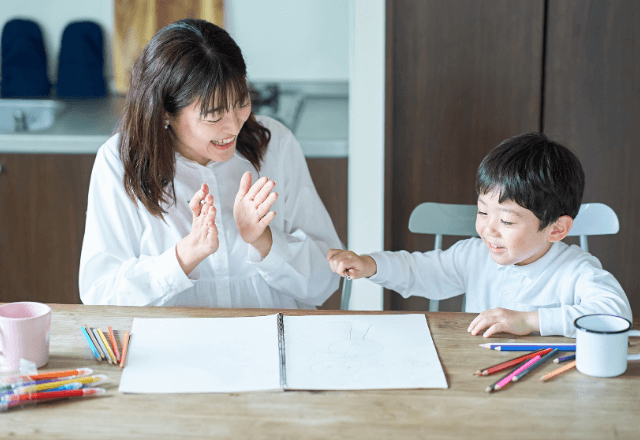
親はつい、子どもの出来ないことが気になりがちですが、小さくても出来たことを探す習慣をつけましょう。 「今日は自分から着替えられたね」「前よりもたくさん食べられたね」と、認める声掛けをしてください。
子どもは認められることで、小さな成功体験を実感することができます。
忙しくて難しいという親御さんは、寝るときにお子さんと今日の良かったところや出来たことを言い合ってみてください。
おやこでポジティブな面に目を向けられるようになり、自己肯定感につながっていきますよ。
くじけない子に育つためには、親の関わり方が大切な役割を持っています。 失敗を恐れず挑戦できる環境をつくり、子どもの気持ちに寄り添った言葉かけをすることで、前向きな心が育ちます。
また、生活習慣を整え、家庭で少しずつ経験を積むことも大切です。
小さな経験の積み重ねが、子どもの未来の大きな力となります。今日からできることを、一つずつ取り入れていきましょう。
監修/ライター:オオイシ(幼稚園教諭二種・保育士・チャイルドカウンセラー)

娘「前に住んでいたお家見てみたい!」妻「いいよ」しかし到着した直後⇒夫「帰...
2024.08.10

【保育士が解説】3歳児ってこんな感じ!発達の特徴やおすすめの遊び方を解説
2023.10.02

【保育士が解説】5歳児の発達と特徴|反抗期がくるって本当?接し方やおすすめ...
2023.10.02

産婦人科で…男性医師の”診察”に違和感を覚えた妊婦。医師の姉に相談した数週...
2024.08.07

強引に『叔父の産院』へ転院させた夫。だが後日⇒「私に任せて」医師の姉が行っ...
2024.08.07

出産前に転院した妻#5
2024.08.07

【ダイソー工作】たった400円で完成する「おうちプラネタリウム」が感動的!...
2021.08.06

夫の帰宅直後…「話がある、ちょっと来て」妻の態度に”違和感”!?その後→妻...
2024.08.01

子どもの「人見知り」への向き合い方|保育士が伝える、サポートのコツ
2025.10.06

出産前に転院した妻#6
2024.08.07