
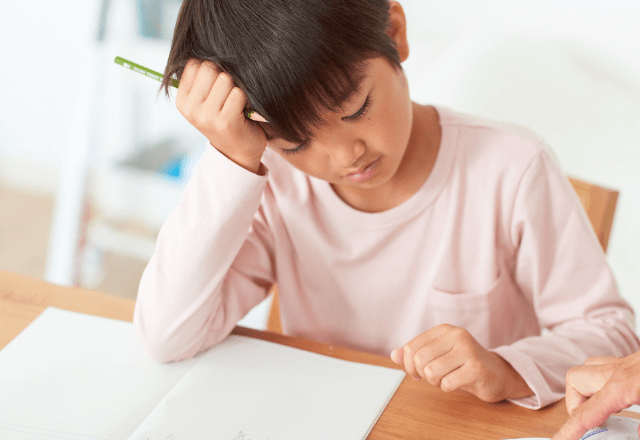
親としては子どものやるべきことをただ確認しているだけのつもり。 でも子どもは「宿題やったの?」という言葉を「どうせやってないんでしょ」という疑いのメッセージとして受け取ってしまうことがあります。
親から「管理されている」「監視されている」と感じたとき子どもの心には反発心が生まれます。 「今やろうと思ってたのに!」とやる気を失ってしまうのです。
この言葉はおやこを監督と選手のような対立関係に立たせてしまいます。
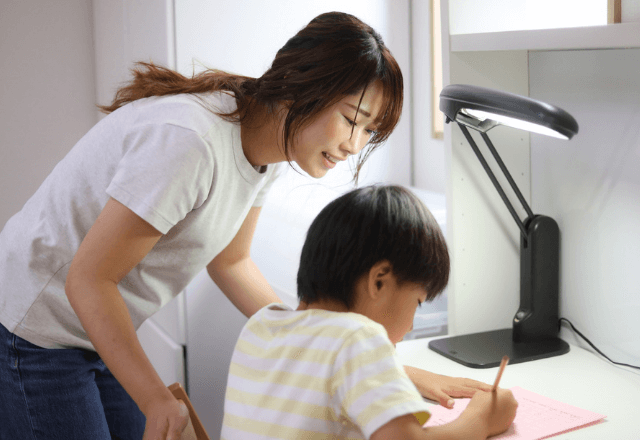
そこで親の役割を「監視役」から「応援団」へと変えてみましょう。 そのための魔法の言葉が「どこか分からないところある?」という問いかけです。
この一言は子どもに「宿題はあなたが自分でやるべきことだと信じているよ」という信頼のメッセージを伝えます。 そしてその上で「もし困っていることがあったらいつでも助ける準備ができているよ」というサポートの姿勢を示すことができます。
この「信頼」と「サポート」の二つのメッセージが子どもの「自分で頑張ってみよう」という主体性を引き出すのです。
「分からないところある?」と聞かれて子どもが素直に「うん、ここが分からない」と言えるかどうか。 それは普段の親子関係が試される瞬間です。
もし子どもが「分からない」と言ったときに親が「どうしてこんな問題が分からないの!」と責めてしまったら。子どもは二度と親に助けを求めなくなります。 親が「そっかこの問題が難しいんだね。一緒に考えてみようか」と穏やかに受け止める。
その安心できる環境があって初めて子どもは自分の弱さや困り事を正直に打ち明けることができるのです。
子どもから「分からない」と助けを求められたとき。 親がすぐに答えを教えてしまうのは一番簡単な方法です。でもそれでは子どもの考える力は育ちません。
応援団である親の役割は答えを教えることではなく答えにたどり着くための「ヒント」を出すことです。
「教科書のどこに似たような問題があったかな?」
「この問題は〇〇くんに何を質問していると思う?」
自分で考え答えを見つけ出したという成功体験。それこそが勉強への本当の自信を育てるのです。

最終的に宿題は親のものではなく子どものものです。 親がサポートはしても代わりにやってあげることはできません。
ときには子どもが宿題を忘れて学校で先生に叱られるという経験も必要なのかもしれません。 その自然な結果から子どもは「自分の行動には責任が伴う」という社会の大切なルールを学んでいきます。
親が子どもの力を信じてどっしりと構えていること。
その姿勢が子どもの中に本当の「責任感」を育てていくのです。
「宿題やったの?」という問いは子どもを管理されるべき「部下」にしてしまいます。 でも「何か分からないところある?」という問いは子どもを共に学ぶ「仲間」にしてくれます。
その温かい関わりが、子どもの中に勉強への前向きな気持ちと、困難に立ち向かうための本当の自信を育てていくのです。 管理の言葉から寄り添いの言葉へ。
そのほんの少しの変化が、おやこの関係をより豊かなものにしてくれるはずです。
ライター / 監修:でん吉(保育士)

娘「前に住んでいたお家見てみたい!」妻「いいよ」しかし到着した直後⇒夫「帰...
2024.08.10

【保育士が解説】3歳児ってこんな感じ!発達の特徴やおすすめの遊び方を解説
2023.10.02

【保育士が解説】5歳児の発達と特徴|反抗期がくるって本当?接し方やおすすめ...
2023.10.02

産婦人科で…男性医師の”診察”に違和感を覚えた妊婦。医師の姉に相談した数週...
2024.08.07

強引に『叔父の産院』へ転院させた夫。だが後日⇒「私に任せて」医師の姉が行っ...
2024.08.07

出産前に転院した妻#5
2024.08.07

【ダイソー工作】たった400円で完成する「おうちプラネタリウム」が感動的!...
2021.08.06

夫の帰宅直後…「話がある、ちょっと来て」妻の態度に”違和感”!?その後→妻...
2024.08.01

子どもの「人見知り」への向き合い方|保育士が伝える、サポートのコツ
2025.10.06

出産前に転院した妻#6
2024.08.07