

「うんちがなかなか出ない…」子どもの排便に悩みを抱えているママやパパは少なくありません。 でも安心してください。排便は個人差が大きく、子どもの体調によっても変わるもの。
焦らずに、子どもに合った排便習慣づくりを心がけることが大切です。
保育現場で培ったノウハウをもとに、少しでもお薬に立てるヒントをお伝えします。
排便習慣を整えるには、規則正しい生活リズムが欠かせません。
食事と睡眠のリズムを整えることが、腸の働きを助けるのです。 朝ごはんをしっかり食べる、なるべく決まった時間に食事をする、十分な睡眠時間を確保する。
そんな生活習慣を心がけることが、子どもの排便リズムを整える第一歩となります。
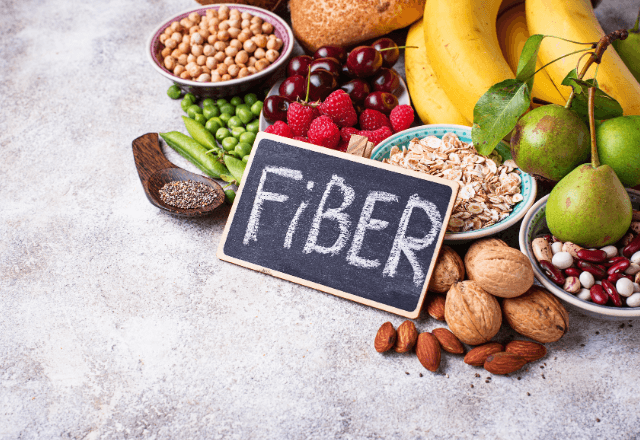
便秘解消には、食事内容も重要です。 特に食物繊維を意識的に取り入れることがポイントです。野菜や果物、豆類、海藻など、食物繊維を多く含む食材を献立に取り入れましょう。
また、乳製品も腸内環境を整える働きがあるので、子どもの様子を見ながら体にあったものを試してみるのもおすすめです。
子どもの好き嫌いに合わせて、少しづつでも工夫しながら食事を提供していきたいですね。
便秘予防に欠かせないのが、水分補給です。
体内の水分が不足すると、便が硬くなり排便が難しくなります。
子どもがこまめに水分を取れるよう、お茶や水を用意しておくことが大切。 甘い飲み物は控えめにし、なるべく水分補給は水や麦茶などで行うのがおすすめです。
子どもの活動量に合わせて、こまめな水分補給を心がけましょう。
慣れないうちは「おトイレの時間だよ」と、排便のタイミングを作ってあげるのも効果的です。
特に朝は腸の働きが活発なので、朝食後にトイレに行く習慣はつけやすい傾向があります。 また、お出かけ前や帰宅後など、生活の節目にトイレに行く時間を設けるのも良いでしょう。
無理強いは禁物ですが、さりげなくトイレに誘導することで、子どもなりの排便リズムが作られていくことがあります。

適度な運動は、腸の働きを活発にしてくれます。
公園で思い切り体を動かしたり、家の中で踊ったりするのもおすすめです。 子どもの年齢や興味に合わせて、楽しく体を動かす機会を作りましょう。
散歩でも、腸の動きを助ける効果が期待できます。 日常的の中に運動を取り入れることで、自然と便秘解消につながっていくはずです。
便秘が続くと、子どもは排便に不安を感じるようになることがあります。
トイレを嫌がったり、便意を我慢したりする様子が見られたら、まずは子どもの不安に寄り添ってあげましょう。「出なくても大丈夫だよ」「痛くないといいね」と、辛抱強く、やさしく声をかけてあげましょう。
好きなキャラクターを用意するなど、トイレの時間をリラックスできる雰囲気にするのも効果的です。 子どもの気持ちに寄り添いながら、排便への苦手意識を和らげていきたいですね。
子どもの排便は、個人差が大きいものです。
なかなかトイレでうんちができなくても、まずは焦らずに見守ることが大切です。 規則正しい生活リズム、食物繊維の摂取、水分補給、トイレのタイミング作り、適度な運動。
そして何より、子どもの不安に寄り添ってあげましょう。 その積み重ねが、子どもの排便習慣づくりにつながっていくのです。
ライター / 監修:でん吉(保育士)

娘「前に住んでいたお家見てみたい!」妻「いいよ」しかし到着した直後⇒夫「帰...
2024.08.10

【保育士が解説】3歳児ってこんな感じ!発達の特徴やおすすめの遊び方を解説
2023.10.02

【保育士が解説】5歳児の発達と特徴|反抗期がくるって本当?接し方やおすすめ...
2023.10.02

産婦人科で…男性医師の”診察”に違和感を覚えた妊婦。医師の姉に相談した数週...
2024.08.07

強引に『叔父の産院』へ転院させた夫。だが後日⇒「私に任せて」医師の姉が行っ...
2024.08.07

出産前に転院した妻#5
2024.08.07

【ダイソー工作】たった400円で完成する「おうちプラネタリウム」が感動的!...
2021.08.06

夫の帰宅直後…「話がある、ちょっと来て」妻の態度に”違和感”!?その後→妻...
2024.08.01

子どもの「人見知り」への向き合い方|保育士が伝える、サポートのコツ
2025.10.06

出産前に転院した妻#6
2024.08.07