
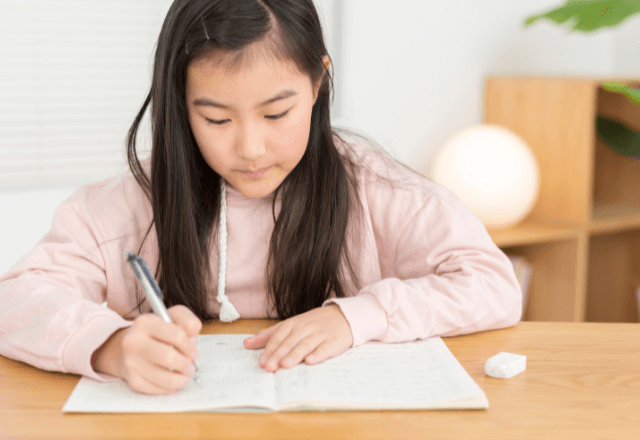
読書感想文を書き始める前に、まずは文章の「構成」を考えることが肝心です。
全体を大きく3つの部分に分け、「序盤」では印象に残ったエピソードをピックアップ、「中盤」で「もし自分だったら」という視点で物語と自分との関連性を考察し、「結論」では読書を通じて自分が何を感じ、何を学んだのかをまとめます。
この際、読み進めるうちに忘れがちなポイントをメモしておくことが重要です。
感動した箇所や驚いた場面、主人公に対する感情など、どのような感想を持ったのかを手短にメモすると実際に書く際に役立ちます。
付箋やノートを活用し、自分の感じたことを随時記録しておきましょう。
文章を書くとき、最初の一文を考えるのは難しいものです。
読書感想文の書き出しでお困りの際は、次のような方法を試してみてください。
まずは、本の感想を一言でまとめて「この本を読んで~と感じました」と書き出す方法。 または、心に残った言葉やフレーズを引用して、そのことについて自分の考えを述べる方法もあります。
さらに、その本を選んだ理由から書き始めると、自然で分かりやすい導入になります。
読書感想文の題名は内容を象徴する大切な一行です。
題名の書き方に決まりはありますが、基本的には2、3マス空けて上から書き始めるのが一般的です。
本の題名を使う場合は、『』で囲み明記します。
ただし、学校やコンテストごとに異なるルールが設けられている場合もあるため、指定されたフォーマットに従うことが大事です。
題名に迷ったときは、本の題名を含めたシンプルな表現、または読んだ本から受けたテーマを題名にするという方法があります。
例えば「友情がテーマなら『友だちの大切さ』、夢がテーマなら『希望を持ち続けて』といった感じです。
読書感想文は、ただの課題と捉えるのではなく、読んだ本から何を学んだか、どう感じたかを共有する貴重な機会です。
感じたことや考えたことを素直に表現することが、読書感想文の醍醐味であり、意図でしょう。
どのような場面に心を動かされ、それが自分や周りの人々にどんな意味を持つのかを見つめ直し、読書を通じて得た感動や学びを深める一助としてみてください。
(おやこのへや編集部)

おやこのへや編集部
心も体も大きく成長する幼児期から小学生の子どもたち。一人ひとりの個性が出てきて、子育てに悩むことも多いこの時期を、おやこで楽しく過ごせるよう、ヒントになる情報を発信していきます。

おやこのへや編集部
心も体も大きく成長する幼児期から小学生の子どもたち。一人ひとりの個性が出てきて、子育てに悩むことも多いこの時期を、おやこで楽しく過ごせるよう、ヒントになる情報を発信していきます。

絶対に開けてはダメと言われた壁の向こうには…#7
2024.09.17

【後編】父の病気に気づいたまさかの理由
2025.10.01

絶対に開けてはダメと言われた壁の向こうには…#8
2024.09.17

運動会で…昼食時、保護者がまさかのバーベキュー開始。学校が注意した結果⇒【...
2025.10.03

子どもを守る防災教育~楽しい学びと学校の取り組み~
2024.08.05

運動会で…確保した場所に見知らぬ保護者が“当然の顔”で相席。言葉を失った直...
2025.10.01

絶対に開けてはダメと言われた壁の向こうには…#9
2024.09.17

絶対に開けてはダメと言われた壁の向こうには…#10
2024.09.17

『ガチャガチャ』深夜の自宅で聞こえた“奇妙な物音”に違和感…直後⇒予想外の...
2025.09.01

『ガチャガチャ』深夜の自宅で聞こえた“奇妙な物音”に違和感…直後⇒予想もし...
2024.08.01