
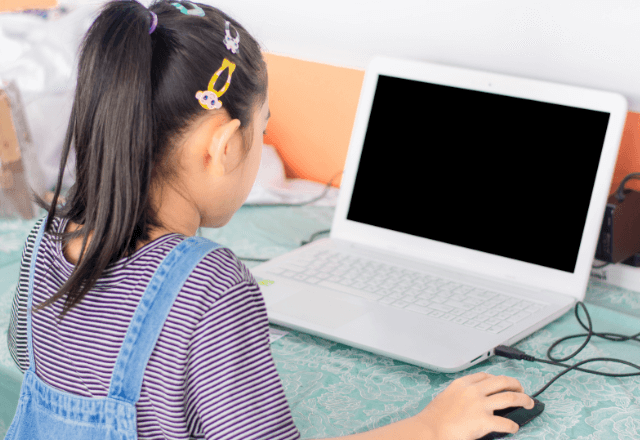
2020年から小学校におけるプログラミング教育が必修化されたことは、教育のあり方における大きな転換点と言えるでしょう。
この決定背景には、IT技術の発展と共に、将来さまざまな職業でITスキルが求められるようになるという文部科学省の見解があります。
日本を含めた世界各国では、高度なIT人材の確保が急務とされ、そのために子どもたちの早い段階からのプログラミング教育が重要視されています。
プログラミング教育の導入により、全ての生徒をプログラマーにすることは目指されていません。
むしろ、この教育の根本的な目的は、プログラミング的思考=論理的思考や問題解決能力の養成にあると文部科学省は説明しています。
このようなスキルは、他の教科の学習や日常生活においても大いに役立ちます。
たとえば、稲作体験が農家を目指すことが目標ではないのと同様、プログラミング教育による様々な経験が、子どもたちの思考力や創造力の拡張に貢献するのです。
それでは、実際の授業ではどのようにプログラミング教育が行われるのでしょうか?特別な時間を設けるのではなく、算数や理科などの既存の教科の中でプログラミングを取り入れるケースが多いです。
例えば、算数の授業で図形のプログラミングを通して作図することで、学びの深化を図るといった方法です。
このように、教科ごとの学習目標を達成するための手段としてプログラミングを活用することが期待されており、それに伴う先生たちへの過剰な専門スキル要求や授業時間の増加は想定されていません。
海外に目を向けると、イギリスやフィンランドなどはすでにプログラミング教育を必修化していますが、教育形態は国によって様々です。
日本のプログラミング教育導入は多くの国と比べやや遅れているものの、必修化に踏み切った意義は大きく、今後の教育改革の一環として注目されています。
必修化されたプログラミング教育は、子どもたちにとって新しい学びの場として、また、将来の社会で活躍するための土台として非常に重要な位置を占めています。
プログラミング的思考を養うことで、子どもたちはさらに多様な角度から物事を考える力を身につけることでしょう。
これからの親世代にとっても、子どもたちと共に新たな学びに触れ、一緒に成長していく機会となるはずです。
(おやこのへや編集部)

おやこのへや編集部
心も体も大きく成長する幼児期から小学生の子どもたち。一人ひとりの個性が出てきて、子育てに悩むことも多いこの時期を、おやこで楽しく過ごせるよう、ヒントになる情報を発信していきます。

おやこのへや編集部
心も体も大きく成長する幼児期から小学生の子どもたち。一人ひとりの個性が出てきて、子育てに悩むことも多いこの時期を、おやこで楽しく過ごせるよう、ヒントになる情報を発信していきます。

絶対に開けてはダメと言われた壁の向こうには…#7
2024.09.17

【後編】父の病気に気づいたまさかの理由
2025.10.01

絶対に開けてはダメと言われた壁の向こうには…#8
2024.09.17

運動会で…昼食時、保護者がまさかのバーベキュー開始。学校が注意した結果⇒【...
2025.10.03

子どもを守る防災教育~楽しい学びと学校の取り組み~
2024.08.05

運動会で…確保した場所に見知らぬ保護者が“当然の顔”で相席。言葉を失った直...
2025.10.01

絶対に開けてはダメと言われた壁の向こうには…#9
2024.09.17

絶対に開けてはダメと言われた壁の向こうには…#10
2024.09.17

『ガチャガチャ』深夜の自宅で聞こえた“奇妙な物音”に違和感…直後⇒予想外の...
2025.09.01

『ガチャガチャ』深夜の自宅で聞こえた“奇妙な物音”に違和感…直後⇒予想もし...
2024.08.01