
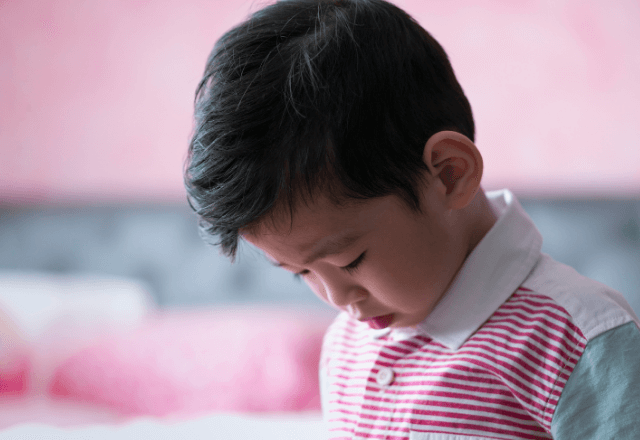

子どもの苦手意識に向き合うためには、まずはその理由を理解することが大切。 「どうして嫌なのかな」と、子どもの気持ちに寄り添ってみましょう。
できない悔しさ、失敗への恐れ、比較されることへの不安。 そんな子どもの心の声に耳を澄ますことが、サポートの第一歩となります。
園でも、子どもの苦手意識の背景を探ることを大切にしています。 「どんなところが難しいんだろう」「どんな風にしたらもっと楽しくなるかな」。 子どもの気持ちを想像しながら、一緒に向き合う。
そこから、克服への道が開けていくはずです。
苦手意識のある子どもには、できることを細かく認めることが何より大切。 「少し走れたじゃん」「すてきな線が引けたね」。ちょっとした成功体験を、しっかりと褒めてあげましょう。
園でも、子どもの小さな一歩ひとつひとつを認め、自信につなげる関わりを心がけています。 苦手なこともできる部分とできない部分があります。 まずはできるところに目を向け、子どもの頑張りを認めてあげること。
その積み重ねが、「苦手」から「少しできる」への扉を開いていくのです。

「苦手」と感じていることの裏には、できないことへの不安や、失敗を恐れる気持ちがあるものです。 だからこそ、失敗を恐れない心を育むことが大切なのです。 「失敗しても大丈夫」「みんな最初できない」そんな風に、失敗を恐れない心の土台を作ってあげましょう。
園でも、子どもたちが安心して挑戦できる雰囲気づくりを大切にしています。
ときには失敗もあるけれど、失敗こそ最大の学びなのです。 一緒に乗り越えれば、もっと大きくなれる。 そんな前向きなメッセージを子どもたちに伝え続けています。
失敗を恐れずチャレンジできる。その心の強さが、苦手意識を克服する原動力になるのだと思います。
「難しいところを一緒に考えるの、面白いね」「ここまでできるようになったんだね」など、苦手に向き合う楽しさを、子どもと一緒に味わってみましょう。
園では、苦手な課題を教え合ったり、達成感を分かち合ったりする活動を大切にしています。 壁を乗り越える過程には、喜びも発見もある。その実感が、苦手意識をポジティブなものに変えていくのです。
「苦手」に向き合うたびに、子どもの心は少しずつ強くなっていきます。 その成長の姿を、しっかりと見守っていきたいですね。
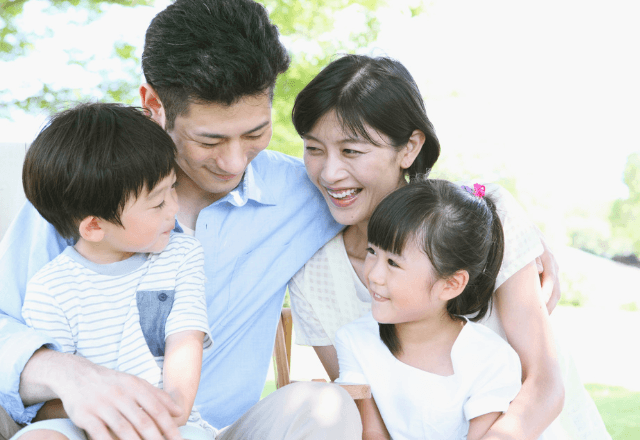
苦手意識のある子どもの力を引き出すためには、周りの理解とサポートも欠かせません。 保護者だけでなく、祖父母や先生、地域の方々など、子どもを取り巻く大人たちに協力を求めていくことも大切で す。
園でも、保護者の方々と連携を取りながら、子ども一人ひとりの特性に合わせた関わりを心がけています。 周りの知恵を借りながら、子どもの苦手意識に向き合う。 そんなチームワークがあれば、道は必ず開けるはず。
みんなで子どもの「できる」を増やしていけたら。 そんな願いを込めて、これからも子どもたちの挑戦を応援していきたいと思います。
子どもの苦手意識への向き合い方は、まずはその理由を理解し、できることを細かく認めること。 失敗を恐れない心を育み、苦手に向き合う楽しさを伝えること。 そして、周りの理解とサポートを得ながら、一緒に前に進むことです。
その積み重ねが、子どもの「苦手」を「得意」に変えていく、あるいは「苦手」なことを認めて、前に進む原動力になるのです。
ライター / 監修:でん吉(保育士)

娘「前に住んでいたお家見てみたい!」妻「いいよ」しかし到着した直後⇒夫「帰...
2024.08.10

【保育士が解説】3歳児ってこんな感じ!発達の特徴やおすすめの遊び方を解説
2023.10.02

【保育士が解説】5歳児の発達と特徴|反抗期がくるって本当?接し方やおすすめ...
2023.10.02

産婦人科で…男性医師の”診察”に違和感を覚えた妊婦。医師の姉に相談した数週...
2024.08.07

強引に『叔父の産院』へ転院させた夫。だが後日⇒「私に任せて」医師の姉が行っ...
2024.08.07

出産前に転院した妻#5
2024.08.07

【ダイソー工作】たった400円で完成する「おうちプラネタリウム」が感動的!...
2021.08.06

夫の帰宅直後…「話がある、ちょっと来て」妻の態度に”違和感”!?その後→妻...
2024.08.01

子どもの「人見知り」への向き合い方|保育士が伝える、サポートのコツ
2025.10.06

出産前に転院した妻#6
2024.08.07