

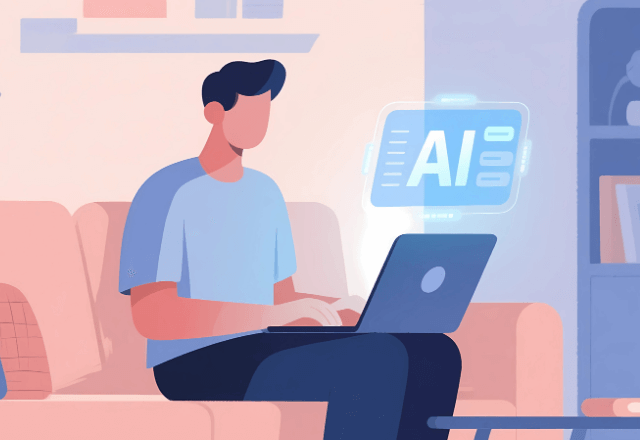
かつて、知識をたくさん持っていることは大きな価値でした。 難しい計算問題を解けること、歴史の年号を暗記していること。それが賢さの証明でした。
しかしAI(人工知能)はその分野において人間をはるかに凌駕します。 膨大なデータを記憶し瞬時に最適な答えを導き出す。その能力において人間がAIに勝つことはできません。
これからの教育はAIが得意なこと、つまり「答えのある問い」に正しく答える能力だけを追い求めるものではなくなるでしょう。
ではAIにはできなくて人間にしかできないこととは何でしょうか。
それは他の人の痛みに寄り添う「共感力」
全く新しいものをゼロから生み出す「創造性」
答えのない問いに対して「なぜ?」と問い続ける「探求心」
そして美しいものを美しいと感じる「感性」
こうした数値化できない心の働きこそが、AIには真似できない人間だけの魔法です。 これからの教育はこうした人間らしい「非認知能力」をいかに豊かに育んでいくかに重点が置かれていくはずです。

AIは与えられた問いに対して最適な答えを出すことは得意です。 しかしAI自身が新しい「問い」を立てることはまだ苦手です。
何が問題なのか。何を探求すべきなのか。その最初の一歩を踏み出す力。 それこそがこれからの時代を生き抜くための最も重要な「羅針盤」になります。
子どもの「なぜ?」という素朴な疑問を大切にする。 すぐに答えを与えるのではなく「あなたならどう思う?」と問い返す。
そうした日々の対話の中で、自分の頭で問いを立て考え続ける習慣を育んでいくことが求められます。
これからの社会は変化が激しく予測不可能です。昨日までの正解が明日には通用しなくなるかもしれません。
そんな時代に必要なのは用意された知識を覚えることよりも、未知の問題にぶつかったときに自分で考え、試行錯誤しながら学び続ける力、つまり「学び方」そのものを身につけることです。
間違いを恐れない。失敗から学ぶ。色々な方法を試してみる。 親が結果だけでなくその試行錯誤のプロセスを認め、応援してあげること。
その経験が子どもの学び続ける力を育てます。
情報が溢れ何が正しいのか見えにくい時代。 だからこそ大切になるのが自分の中にしっかりとした「軸」を持つことです。
自分は何を大切にしたいのか。どんなときに喜びを感じるのか。
周りの意見や流行に流されるのではなく、自分の心の声に耳を澄まし、自分で判断し決断する力。 子どもの「好き」という気持ちを尊重し、自分で選択する経験をたくさん積ませてあげること。
それが揺るがない自分軸を育むための土台になります。
AI時代だからといって、考える力が全く不要になるわけでは決してありません。 むしろこれからはAIにはできない「人間ならではの考え方」がより一層重要になってきます。
知識を覚えることよりも問いを立てること。 正解を求めることよりも創造すること。 そして何よりも他の人の心を思いやり、自分自身の心を大切にすること。
その人間としての根源的な力を育むことこそが、どんな時代にも揺るがない最高の教育なのかもしれません。
ライター / 監修:でん吉(保育士)

娘「前に住んでいたお家見てみたい!」妻「いいよ」しかし到着した直後⇒夫「帰...
2024.08.10

【保育士が解説】3歳児ってこんな感じ!発達の特徴やおすすめの遊び方を解説
2023.10.02

【保育士が解説】5歳児の発達と特徴|反抗期がくるって本当?接し方やおすすめ...
2023.10.02

産婦人科で…男性医師の”診察”に違和感を覚えた妊婦。医師の姉に相談した数週...
2024.08.07

強引に『叔父の産院』へ転院させた夫。だが後日⇒「私に任せて」医師の姉が行っ...
2024.08.07

出産前に転院した妻#5
2024.08.07

【ダイソー工作】たった400円で完成する「おうちプラネタリウム」が感動的!...
2021.08.06

夫の帰宅直後…「話がある、ちょっと来て」妻の態度に”違和感”!?その後→妻...
2024.08.01

子どもの「人見知り」への向き合い方|保育士が伝える、サポートのコツ
2025.10.06

出産前に転院した妻#6
2024.08.07