


友だちとうまく遊べない子どもへの関わり方で大切なのは、まずは子どもの興味関心に寄り添うこと。 一人遊びが好きな子、特定の遊びに熱中する子など、その子なりの遊びのスタイルがあるはずです。
園でも、子ども一人ひとりの個性を大切にしながら、その子に合った遊びを提供するようにしています。
ご家庭でも、子どもの好きな遊びを一緒に楽しんでみてください。 「電車が好きなんだね」「ブロック遊び、上手だね」と、子どもの世界に共感的に入っていくことが、社会性の土台作りにつながります。
子どもの興味を理解し、受け止めてあげる姿勢が子どもの心を開くカギになります。
友だちとの関わりが苦手な子どもには、少しずつ小集団での遊びを体験させることが効果的です。
園では、2〜3人の小グループで遊ぶ機会を多く設けています。 ごっこ遊びやボードゲームなど、役割のある遊びを通して、自然とコミュニケーションが生まれるのです。
ご家庭でも、公園などで小集団の遊びに誘ってみてはいかがでしょうか。 最初は緊張するかもしれません。でも、子どもの様子を見守りつつ「一緒に遊ぼうよ」と優しく背中を押してあげてください。
小さな集団での遊びの積み重ねが、徐々に友だちと関わる心地よさを教えてくれるはずです。
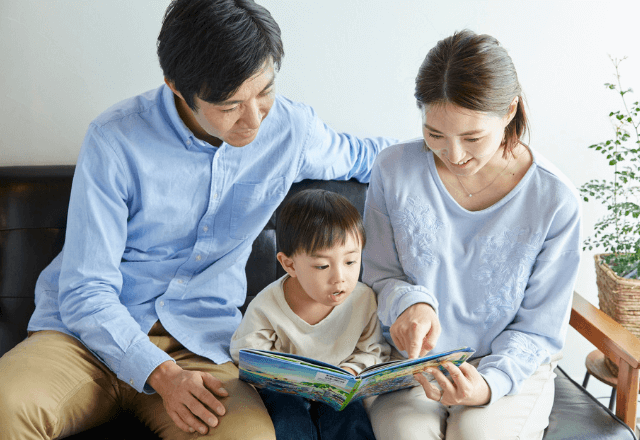
友だちとうまく遊べない子どもには、コミュニケーションの取り方を具体的に教えていくことも大切です。
園では、保育士が友だちとの関わり方のお手本を示すようにしています。 「一緒に遊ぼう」と誘う言葉かけ、順番を待つ態度、おもちゃを貸し借りする際のやり取りなど、子どもの目の前でコミュニケーションのモデルを示すのです。
ご家庭でも、ママやパパが友だちと楽しく会話する姿を見せてあげましょう。
「おもちゃ貸してくれてありがとう」「一緒に遊べて嬉しいな」。
そんな何気ない言葉のやり取りが、子どもにとってのお手本になります。
大人が示すコミュニケーションの在り方を、子どもは敏感に学んでいくのです。
何より大切なのは、友だちとうまく遊べない子どものペースに合わせて、ゆっくりと関わっていくこと。
社会性の発達には個人差があるもの。 急がせたり、強制したりせずに、子どものペースを尊重することが何より重要です。
園でも、一人ひとりの成長に寄り添いながら、長い目で子どもの変化を見守っています。
ご家庭でも、今日より明日、明日より明後日と、子どもなりのスピードで少しずつ成長していけるよう、あたたかく見守ってあげてください。 ときには「お友だちと遊びたくない?」と尋ねてみるのもおすすめ。
子どもの気持ちに耳を傾け、おやこの信頼関係を築いていくことが、社会性の芽生えを支える土台になるのです。

友だちと遊ぶことに不安を感じている子どもには、小さな成功体験の積み重ねも大切にしましょう。
「お友だちと一緒に滑り台を滑れたね」「おもちゃを貸してあげられたね」と、ささやかでも、友だちとの関わりの中で感じた喜びを、たくさん言葉にしてあげましょう。 園でも、子どもたちの小さな一歩ひとつひとつを認め、自信につなげる関わりを大切にしています。
ご家庭でも、子どもの頑張りにしっかりと目を向け、具体的に褒めてあげる習慣つけてあげてください。 「友だちと遊ぶのは楽しい」そんな気持ちが少しずつ芽生えてくるはずです。
小さな成功体験を重ねる中で、子どもは確実に成長していきます。
友だちとうまく遊べない子どもへの接し方は、まず子どもの興味関心に寄り添い、小集団での遊びの機会を作ること。 そして、コミュニケーションのモデルを示しつつ、子どものペースを尊重すること。 小さな成功体験を積み重ねる中で、社会性の芽生えを優しく励ましていく。
その積み重ねが、友だちと心地よく関われる子どもへと導いていくのです。
保育士として、たくさんの子どもたちの社会性の育ちに立ち会ってきました。 一人遊びが好きだった子も、少しずつ友だちの輪に加わるようになる。 ぎこちなかった会話も、次第に弾むようになっていきます。
ご家庭でも、どうか焦らずに、子どもの成長を信じてあげてください。 ゆっくりでも着実に、友だちの中にその子の居場所ができていきます。
ライター / 監修:でん吉(保育士)

娘「前に住んでいたお家見てみたい!」妻「いいよ」しかし到着した直後⇒夫「帰...
2024.08.10

【保育士が解説】3歳児ってこんな感じ!発達の特徴やおすすめの遊び方を解説
2023.10.02

【保育士が解説】5歳児の発達と特徴|反抗期がくるって本当?接し方やおすすめ...
2023.10.02

産婦人科で…男性医師の”診察”に違和感を覚えた妊婦。医師の姉に相談した数週...
2024.08.07

強引に『叔父の産院』へ転院させた夫。だが後日⇒「私に任せて」医師の姉が行っ...
2024.08.07

出産前に転院した妻#5
2024.08.07

【ダイソー工作】たった400円で完成する「おうちプラネタリウム」が感動的!...
2021.08.06

夫の帰宅直後…「話がある、ちょっと来て」妻の態度に”違和感”!?その後→妻...
2024.08.01

子どもの「人見知り」への向き合い方|保育士が伝える、サポートのコツ
2025.10.06

出産前に転院した妻#6
2024.08.07