


ごっこ遊びの最大の特徴。それは「自分ではない誰か」になることです。
お母さんになったり赤ちゃんになったり。先生になったり、ときには犬や猫になったり。 その「なりきり」の中で子どもは「ママはこんなときどんな気持ちかな?」「赤ちゃんはどうしてほしいかな?」と、相手の視点に立って物事を想像します。
この想像力のジャンプこそが、人の痛みがわかる「共感力」や思いやりの心を育む、最初の教室です。 保育士は、この「なりきり」の深まりをじっと見守っています。
ごっこ遊びは決して一人では完結しません。そこには必ず他者との関わりがあります。
「私がお店屋さんね」「ぼくもやりたい!」「じゃあじゅんばんこしよう」「あなたはレジ係ね」。
自分の欲求を主張し、相手の要求を聞き、そしてお互いが納得できる妥協点を見つける。 これは大人が社会で行っている「交渉」そのものです。
集団の中でうまく遊ぶためのルールを、自分たちで作り上げていく。 保育士は、この高度な社会性が育つ貴重な瞬間を邪魔しないように、ただ安全を確保しながら見守っています。
ごっこ遊びは言葉の宝庫です。
子どもはその役になりきるために、自分が知っている全ての語彙を総動員します。 普段は使わないような「おいくらですか?」「診察しますね」といった大人びた言葉。 それらを実際に使ってみることで、言葉はその子の血肉になっていきます。
またお友だちとのやり取りの中で「こう言えば伝わるんだ」「今は黙って聞く番だ」という、コミュニケーション能力そのものが実践的に磨かれていきます。
これはドリルでは学べない、生きた言葉のレッスンです。
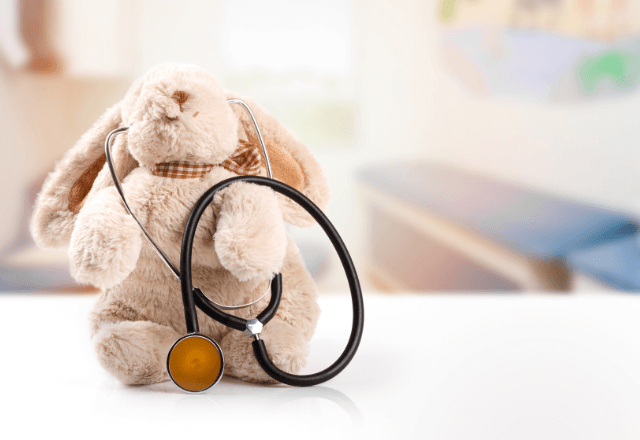
私たち保育士が特に注目しているのがこの側面です。 ごっこ遊びは子どもの心のデトックスの役割を果たします。
例えば歯医者さんで怖い思いをした子が、園でさっそく歯医者さんごっこを始めることがあります。 自分が治す側の強い立場になることで、その怖かった経験を自分の力で乗り越えようとしているのです。
親に叱られた経験を、おままごとでお人形相手に再現してみる。 そうやって自分の感情を客観的に見つめ直し心を整理していることもあります。
私たちはその健気な心の働きを大切にしています。
一つの積み木を「もしもし」と電話に見立てる。 砂場のお団子を「ごちそうですよ」とお皿に乗せる。
この「〇〇を△△と見立てる」力。それはただの空想ではありません。
目の前にないものを想像する「創造力」であり、やがて文字や数字といった「抽象的な概念」を理解するための大切な土台になります。 この見立てる力こそが、将来のあらゆる学びの基礎体力を作っているのです。
保育士は、その想像力を折らないよう環境を整えます。
ごっこ遊びはただの遊びではありません。 それは子どもにとって社会を学び、言葉を獲得し、心を癒し、そして未来を創造するための最も重要な仕事です。
だから私たち保育士は子どもが夢中になってごっこ遊びをしている、そのかけがえのない時間を何よりも大切に守っているのです。ご家庭でもぜひその豊かな世界に飛び込んでみてください。
ライター / 監修:でん吉(保育士)

娘「前に住んでいたお家見てみたい!」妻「いいよ」しかし到着した直後⇒夫「帰...
2024.08.10

【保育士が解説】3歳児ってこんな感じ!発達の特徴やおすすめの遊び方を解説
2023.10.02

【保育士が解説】5歳児の発達と特徴|反抗期がくるって本当?接し方やおすすめ...
2023.10.02

産婦人科で…男性医師の”診察”に違和感を覚えた妊婦。医師の姉に相談した数週...
2024.08.07

強引に『叔父の産院』へ転院させた夫。だが後日⇒「私に任せて」医師の姉が行っ...
2024.08.07

出産前に転院した妻#5
2024.08.07

【ダイソー工作】たった400円で完成する「おうちプラネタリウム」が感動的!...
2021.08.06

夫の帰宅直後…「話がある、ちょっと来て」妻の態度に”違和感”!?その後→妻...
2024.08.01

子どもの「人見知り」への向き合い方|保育士が伝える、サポートのコツ
2025.10.06

出産前に転院した妻#6
2024.08.07