

まずは、ケガの種類と程度を正確に把握することが大切です。 切り傷、擦り傷、打撲、捻挫など、ケガの種類によって対応方法は異なります。
保育士から詳しい状況を聞き、ケガの部位や大きさ、出血の有無などを確認しましょう。軽度のケガであれば、過度に心配する必要はありません。子どもの様子を見守りつつ、園の対応を信頼することが肝心です。
一方で、医療機関の受診が必要なケースもあります。 頭部のケガ、意識の変容、激しい痛みを伴うケガなどは、速やかに病院で診てもらうことが大切です。
また、傷が深い、出血が止まらない、変形や腫れが著しいなどの場合も、医療機関の受診が必要です。こうしたケースでは、園から連絡があり次第、冷静に対応することが求められます。子どもの安全を最優先に、園と連携して適切な処置を図りましょう。
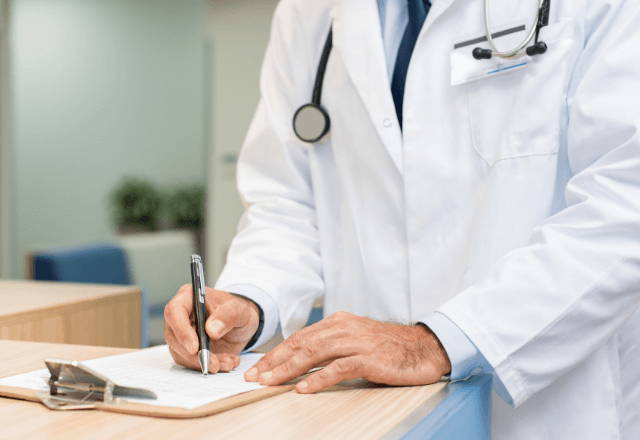
園でのケガを心配するあまり、子どもの行動を過度に制限してしまっては、かえって成長の妨げになってしまいます。 むしろ、ケガの予防に向けた園の取り組みを知ることが大切です。 安全点検の実施、危険箇所の改善、保育士の配置や監督体制など、園がケガの防止にどのように努めているのか、保育士に尋ねてみましょう。園の安全対策を理解することで、ケガへの不安も和らぐはずです。
家庭でも、ケガの予防と事後の対応を心がけたいものです。 子どもの発達段階に合った遊び方を選び、危険な行為には注意を促しましょう。また、ケガをしたときは、傷口を清潔に保ち、様子を見守ることが大切です。痛みや腫れが続く場合は、迷わず医療機関を受診しましょう。園での様子も保育士に確認し、ケガの回復状況を共有することが肝心ですね。
ケガは、成長の過程で誰もが経験するものです。
むしろ、ケガを通して学ぶことも多いのです。痛みを知る、危険を察知する、失敗から学ぶ。 そうした経験の積み重ねが、子どもの自己防衛能力を高めていくのです。
もちろん、危険を避けるための配慮は必要ですが、ケガを恐れるあまり子どもの挑戦を阻んではいけません。ケガを成長の機会ととらえ、子どもの冒険心を応援する姿勢も大切にしたいものです。

保育園でのケガは、保護者にとって心配な出来事ですが、過度に怖がる必要はありません。 ケガの種類や程度を見極め、必要な場合は医療機関を受診する。そして、ケガの予防に向けた園の取り組みを知り、家庭でもできる対策を講じる。
何より大切なのは、ケガと向き合うときの冷静な判断力と、子どもの成長を信じる前向きな姿勢です。
一つひとつのケガに寄り添い、子どもの痛みに共感する。そして、ケガの経験を通して、子どもたちは少しずつ逞しく成長していく。そんな子どもたちの姿に、保育の喜びを感じずにはいられません。ご家庭でも、どうかケガに臆することなく、子どもの可能性を信じる目線を忘れずに。きっと、ケガの経験もまた、かけがえのない成長の糧になるはずです。
ライター/監修:でん吉(保育士資格)

娘「前に住んでいたお家見てみたい!」妻「いいよ」しかし到着した直後⇒夫「帰...
2024.08.10

【保育士が解説】3歳児ってこんな感じ!発達の特徴やおすすめの遊び方を解説
2023.10.02

【保育士が解説】5歳児の発達と特徴|反抗期がくるって本当?接し方やおすすめ...
2023.10.02

産婦人科で…男性医師の”診察”に違和感を覚えた妊婦。医師の姉に相談した数週...
2024.08.07

強引に『叔父の産院』へ転院させた夫。だが後日⇒「私に任せて」医師の姉が行っ...
2024.08.07

出産前に転院した妻#5
2024.08.07

【ダイソー工作】たった400円で完成する「おうちプラネタリウム」が感動的!...
2021.08.06

夫の帰宅直後…「話がある、ちょっと来て」妻の態度に”違和感”!?その後→妻...
2024.08.01

子どもの「人見知り」への向き合い方|保育士が伝える、サポートのコツ
2025.10.06

出産前に転院した妻#6
2024.08.07