
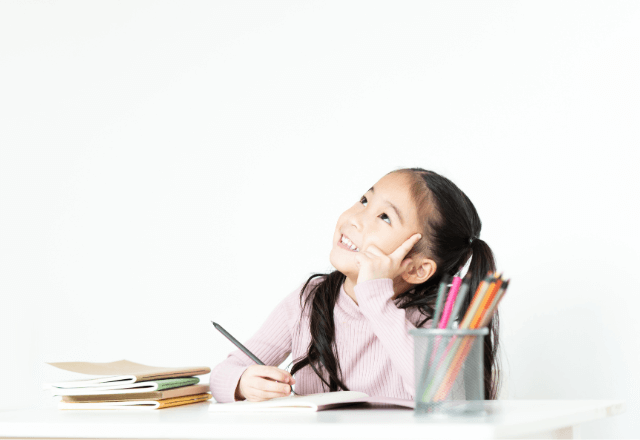
「自分で考える力」とは、まわりの状況を見ながら自分なりに判断し、どう動くかを決めて実行する力のこと。 自分で決めて行動するからこそ、その結果についても責任を持つ力が自然と育っていきます。
教育でも「これからの予測できない時代を生き抜くには、自分で考え、選び、動ける力が大切」とされています。 つまり、子どもたちには、正解のない問題に向き合って、自分なりの答えを出す力が求められているんですね。
「考える力」を育てるためには、一つの見方にとらわれず、さまざまな視点から物事を見る「多角的な思考」が大切です。 さらに「どうしてこうなるのか?」を順を追って説明できる「論理的な思考力」も必要になってきます。
こうした考え方は、問題をシンプルに整理して、スムーズに解決する力にもつながっていきます。
考える力は、特別なトレーニングをしなくても、日々のやりとりの中で育てることができます。
たとえば、子どもが「これやってもいい?」とお願いしてきたとき、すぐに「いいよ」「ダメ」と答えるのではなく、 「どうしてそう思ったの?」と理由を聞いてみると、子どもは自然と自分の考えを整理しようとします。
また、子どもからの質問にもすぐに答えるのではなく「どうしてだと思う?」と問い返してみるのもおすすめです。 こうしたやりとりが、子どもが自分で考えるきっかけをつくってくれます。
さらに、「今日はどっちの服を着る?」「どれをおやつに選ぶ?」など、選択肢を与えることも良い練習になりますよ。
日常生活における些細なやり取りが、子どもが考える力を伸ばせるヒントがたくさんあります。 おやこで対話を楽しみながら、子どもが自分の考えを持てるように見守っていきたいですね。
大人が「子どもの気づき」や「やってみたい」という気持ちを大切にすること。 それが、子どもが自信を持って自分で考え、動ける力を育てる第一歩になるかもしれません。
(おやこのへや編集部)

おやこのへや編集部
心も体も大きく成長する幼児期から小学生の子どもたち。一人ひとりの個性が出てきて、子育てに悩むことも多いこの時期を、おやこで楽しく過ごせるよう、ヒントになる情報を発信していきます。

おやこのへや編集部
心も体も大きく成長する幼児期から小学生の子どもたち。一人ひとりの個性が出てきて、子育てに悩むことも多いこの時期を、おやこで楽しく過ごせるよう、ヒントになる情報を発信していきます。

絶対に開けてはダメと言われた壁の向こうには…#7
2024.09.17

【後編】父の病気に気づいたまさかの理由
2025.10.01

絶対に開けてはダメと言われた壁の向こうには…#8
2024.09.17

運動会で…昼食時、保護者がまさかのバーベキュー開始。学校が注意した結果⇒【...
2025.10.03

子どもを守る防災教育~楽しい学びと学校の取り組み~
2024.08.05

運動会で…確保した場所に見知らぬ保護者が“当然の顔”で相席。言葉を失った直...
2025.10.01

絶対に開けてはダメと言われた壁の向こうには…#9
2024.09.17

絶対に開けてはダメと言われた壁の向こうには…#10
2024.09.17

『ガチャガチャ』深夜の自宅で聞こえた“奇妙な物音”に違和感…直後⇒予想外の...
2025.09.01

『ガチャガチャ』深夜の自宅で聞こえた“奇妙な物音”に違和感…直後⇒予想もし...
2024.08.01