
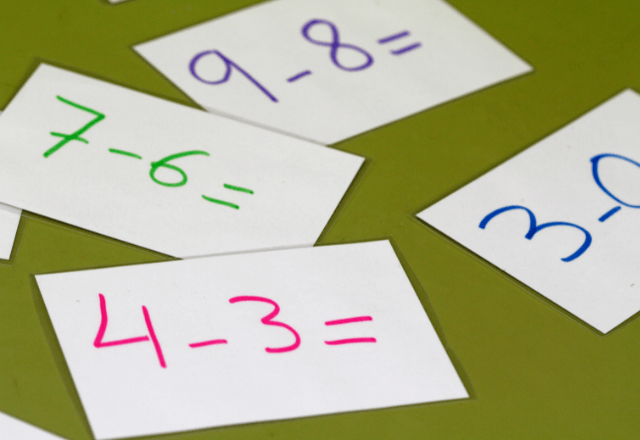
小学校入学を控えた子どもたちにとって、引き算は算数の新たな挑戦です。
引き算を理解するためには、まずその概念から始めましょう。
「物が減ること=引き算」という基本的な考え方を、日常生活でのささいなできごとを通じて教えることがポイントです。
たとえば、おやつを食べた後の数の変化を一緒に確認するといった方法があります。
何よりも大切なのは、子どもが自然と引き算の意味を体感できるような環境を整えることです。
引き算を教える次のステップは、物を使った視覚的な学習です。
ラムネやチョコレートなど、子どもが好きなお菓子を用いて、「5個あったお菓子から3個食べると、あといくつ残る?」といった形で、実際に数を減らしてみせることで、引き算の過程を楽しく学びます。
このとき、子どもが自分で数を数えられるよう、指導者は導く役割に徹することが重要です。
また、ブロックや積み木といった、身近にあるアイテムも活用しましょう。
子どもが引き算に少し慣れてきたら、サクランボ計算を紹介します。
サクランボ計算は、特に繰り下げのある計算を楽しみながら学べる方法です。
たとえば、「12から7を引く」場合、「12」を「10+2」へと分解し、次に「10-7=3」の計算を行い、最後に「3+2=5」と答えを導きます。
この方法を通じて、子どもは複雑な引き算にも柔軟に対応できるようになります。
算数が苦手な子どもへの一番の対策は、学ぶ過程を楽しいものに変えることです。
具体的な対策として、100玉そろばんの使用を提案します。
この道具を使えば、子ども達は視覚的にも分かりやすく、10の位の概念を含めた引き算を理解しやすくなります。
IKEAやボーネルンドなどからもさまざまな教育玩具が販売されているので、子どもの興味に合わせて選択してみてください。
引き算を学ぶことは、子どもの算数における大事な一歩です。
日常生活でのささいな出来事を通じて引き算の概念を紹介することから始め、徐々に実際の計算へと進めていきましょう。
そして何より、子どもが算数を楽しいと感じられるような学習方法を提供することが、算数への好奇心を育んでいく上で非常に重要です。
(おやこのへや編集部)

おやこのへや編集部
心も体も大きく成長する幼児期から小学生の子どもたち。一人ひとりの個性が出てきて、子育てに悩むことも多いこの時期を、おやこで楽しく過ごせるよう、ヒントになる情報を発信していきます。

おやこのへや編集部
心も体も大きく成長する幼児期から小学生の子どもたち。一人ひとりの個性が出てきて、子育てに悩むことも多いこの時期を、おやこで楽しく過ごせるよう、ヒントになる情報を発信していきます。

絶対に開けてはダメと言われた壁の向こうには…#7
2024.09.17

【後編】父の病気に気づいたまさかの理由
2025.10.01

絶対に開けてはダメと言われた壁の向こうには…#8
2024.09.17

運動会で…昼食時、保護者がまさかのバーベキュー開始。学校が注意した結果⇒【...
2025.10.03

子どもを守る防災教育~楽しい学びと学校の取り組み~
2024.08.05

運動会で…確保した場所に見知らぬ保護者が“当然の顔”で相席。言葉を失った直...
2025.10.01

絶対に開けてはダメと言われた壁の向こうには…#9
2024.09.17

絶対に開けてはダメと言われた壁の向こうには…#10
2024.09.17

『ガチャガチャ』深夜の自宅で聞こえた“奇妙な物音”に違和感…直後⇒予想外の...
2025.09.01

『ガチャガチャ』深夜の自宅で聞こえた“奇妙な物音”に違和感…直後⇒予想もし...
2024.08.01